『縁もゆかりもあったのだ』(こだま・著/太田出版・刊)は、覆面作家のこだまさんが、ウェブ上で一年にわたって連載された”旅”にまつわるエッセイに加筆修正をして一冊にまとめたものだ。こだまさんといえば私小説『夫のちんぽが入らない』で鮮烈なデビューをしたが、北国の田舎町に暮らしていること、主婦であることなどわかっている素性はわずかしかない。彼女が作家であることは編集者をはじめとしたごく一部の人以外、家族すら知らないのだという。が、こだまさんのエッセイはとてもおもしろく、文章にリズムがあって読みやすくファンが多い。かくいう私もそのひとりなのだ。
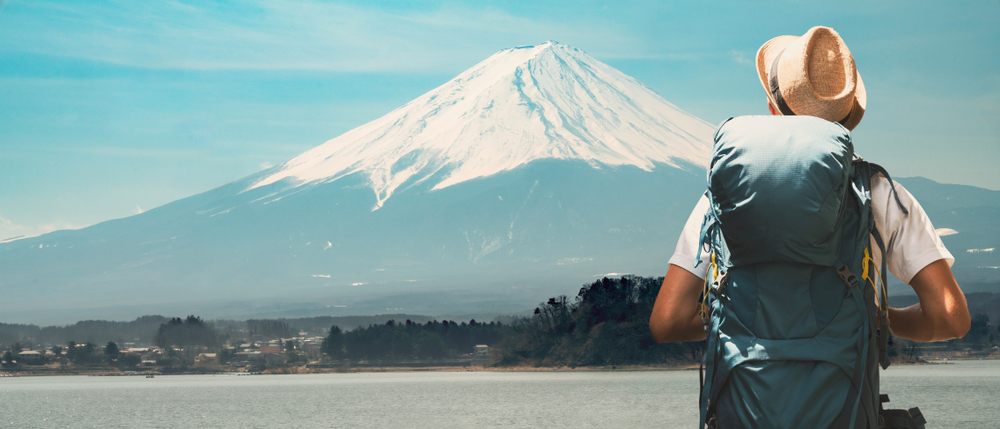
初めて訪れた土地が初めてではないことも?
本作について、こだまさんはこう語っている。
自分とは無関係だと思い込んでいた人や土地が、その細い糸を辿っていくと、つながっていた。何気なく通り過ぎた場所が数十年の時を超えて急に意味を持つ瞬間もある。そんな過去の記憶とのつながりもまた、旅ではないか。(中略)何かを見たり聞いたり触れたりすると、大事なものや忘れかけていた些細な出来事が、わっと降りてくる。それを整理しないまま話すのでは伝わらない。「こじつけや妄想はいけない」と、いつも注意されていた。言葉にはださないけれど、点と点を結ぶ作業は頭の中で続けていた。『縁もゆかりもあったのだ』は、そんな少女時代に押しやった声を自由に出していい場所になった。
(『縁もゆかりもあったのだ』から引用)
コロナ禍で、自由に旅ができないこの夏だから、こだまさんのエッセイを読みつつ、誰にでもある土地にまつわる古い記憶を呼び起こしてみるのも悪くない。
ポストカードの中の京都
子ども時代のこだまさんは赤面症で友だちづくりに苦労したという。そんな彼女の心の拠り所だったのが文通だった。京都に住む同い年のチカちゃんという女の子とは、互いに「いらないものを交換する」というやりとりをしていたそうだ。こだまさんが使い捨てカイロや御守りなどを送ると、チカちゃんからは京都のポストカードを数枚送ってきた。北国の集落からほとんど出たことがないこだまさんにとって、ポストカードの風景は初めて触れる生身の異文化。中でも目を奪われたのは赤茶けたレンガの橋「水路」だったと振り返る。文通は5年ほど続いたものの、やがて間隔が長く開くようになっていき自然と手紙のやり取りはなくなった。
時は流れ、30代になったこだまさんは、ひとり旅をしよう、京都に行こうと決め、ガイドブックを買ってページをめくると、あの「水路」があった。
知ってる。私この場所、ずっと前から知ってる。チカちゃんの送ってくれたポストカード。あの「水路」だ。四月初旬の京都の街をひとり歩いた。(中略)私の足は京都市の東側、南禅寺に向かった。寺のシンボルとなっている荘厳な三門を抜け、境内の片隅に視線を移すと不意にそれが目に入った。「あ、チカちゃんの水路」思わず声に出していた。(中略)初めて訪れたのに、初めてじゃない。懐かしさが込み上げてくる。
(『縁もゆかりもあったのだ』から引用)
写真や映像で見たことのある風景が、目の前に現れると、ふいに懐かしい気持ちになることが私にもある。自分とその場所になにか繋がりがあるのかはいつもわからずじまいなのだが……。
東京は縁のない場所だった
現在、こだまさんは編集者との打ち合わせなど仕事で月一で通うようになった東京だが、そもそもは縁のない場所だったという。東京を知らない、何をすればいいのかわからない、そんなぼんやりとした怖さがあって東京を避けていたのだそうだ。封印が解けたのは2010年のことで、同じ投稿サイトの仲間20人と東京で会うことになった。都心だと山暮らしのこだまさんが辿り着けないだろうと配慮して場所は蒲田になった。
「蒲田なら空港からすぐだから大丈夫だよ」と言われたが、東京に大丈夫な場所があるとは思えなかった。ひとりでちゃんと電車に乗れるだろうか。三十歳をとうに過ぎているのに、そんな初歩的なところで躓いてしまう。私の故郷には線路すら通っていない。バスは一日二本。とても難易度の高いミッションにしか思えない。
(『縁もゆかりもあったのだ』から引用)
このくだりを読んでいたら、自分が上京した日を思い出していた。地方都市出身の私でも、はじめての東京は緊張し、新幹線を降りて山手線に乗り換えるのもウロウロひと苦労したのだった。こんな風に、こだまさんのエッセイは彼女の体験を綴っているのにもかかわらず、読者の記憶をも呼び覚ましてくれるのだ。
ロンドンで出会ったクジャクとリス
こだまさんが初めて海外を訪れたのは新婚旅行で「ロンドン、パリ、ローマ七泊八日」のツアーに参加したとき。食欲も物欲もある他の参加者と比べ、こだまさん夫婦は異国に居ながら何も浮かばない垢抜けない存在になっていたという。けれどもご主人はそんな状況を面白がっていたそうだ。
ロンドンではホテルから歩いて近い「ホランド・パーク」で飽きることなく過ごした半日を綴っている。公園は見渡せるような規模ではなく、森を歩いているよう。不意に草むらが音を立てて揺れたので身構えると、なんと色鮮やかなクジャクが現れた。パンをちぎって投げると飛びついたので、こだまさん夫婦はヘンゼルとグレーテルのようにパンくずをこぼしながら小道をあるいたのだそうだ。
振り返ると、どこに潜んでいたのかクジャクが増えていた。パンをめぐって喧嘩も勃発している。地元の子どもたちが指をさして笑う。私たちはクジャクを連れまわす日本人になっていた。その公園にはリスもいた。(中略)彼らもまた人間に擦り寄ってくる。私たちは売店でピーナッツを買い、リスの小さな手に渡した。するとあっという間にリスに囲まれた。その傍らには先ほどのクジャクもいる。
(『縁もゆかりもあったのだ』から引用)
海外旅行に出かけたとき、あえて街に繰り出さなくても、こんな楽しい体験ができることをこだまさんは教えてくれる。
この他にも、どんな土地でも気取らず自然体のまま行動するこだまさんの旅の話は、とにかく痛快だ。本書を読めば、ステイホームをしなければならない夏のひとときをきっと楽しく過ごせるだろう。
【書籍紹介】

縁もゆかりもあったのだ
著者:こだま
発行:太田出版
初めて訪れたのに、初めてじゃない。京都、ハワイ、病院、引っ越し。場所と記憶をめぐる、笑いと涙の紀行エッセイ。
