本を捨てるのが苦手だ。家事の中で、本箱の掃除が一番、嫌い……。何とかして本を減らそうと頑張っているのだが、別れはつらく、どうしようか迷いながら再読しているうち、半日が経ってしまったりする。
一年に一度、年末の大掃除で泣く泣く処分するのだが、それでも捨てられない本もある。大掃除を乗り越え、しぶとく生き残ってしまうのだ。表紙は破れ、ページは茶色く変色し、さんざんな姿になりながらも、本箱の一番、良い場所に生息し続ける。『神戸・続神戸・俳愚伝』(西東三鬼・著/講談社・刊)も、生き残り組の一冊で、何度もの危機をかいくぐってきた。

シンガポールでの青春
『神戸・新神戸・俳愚伝』の著者・西東三鬼は、1900年生まれの俳人だ。三鬼は雅号で、本名を斎藤敬直という。両親を早くに亡くしたため、兄のもとで育ち、長じて歯科医となってからも、兄を頼りに生活したようだ。兄の赴任地であるシンガポールについていき、歯科医院を開業している。自分で望んで始めた海外生活ではないが、熱帯の暮らしが彼を一変させたようだ。
シンガポール時代の三鬼は、すべてを取り戻そうと全方位に向けてはばたいた。外国人と遊興する一方で、日本より古典文学書を取り寄せ耽読。シンガポールという「赤道直下の乳香と没薬の国」(『俳愚伝』)で、日本古典を読むという、一見ミスマッチな生活が、後の俳人三鬼のバックボーンを作ることになる
(『神戸・続神戸・俳愚伝』解説より抜粋)
人間は異文化の中に放り込まれると、化学反応を起こしたかのように、自分を変えてしまうときがある。シンガポールに移住した西東三鬼にも同じことが起こった。生まれ変わったように、三鬼は希望に満ちた生活を送るようになる。熱帯での暮らしと相性がよかったのだろう。
けれども、結局、三鬼のシンガポール生活は三年で終了となった。対日感情が悪化し、日本排斥運動が始まったためだ。さらには、チフスに罹って生死の境をさまよい、帰国を余儀なくされた。
三鬼にとっては、残念な帰郷であったろう。しかし、物事には良いことと悪いことがある。シンガポールを追われ、体も壊し、「亡霊のような異邦人」となった彼だったが、知り合いに勧められた俳句の世界と出会い、生気をとりもどした。自分を救うための何かを求めていた三鬼は、俳句に魅了され、次々と驚くような斬新な句を発表し始める。
水枕ガバリと寒い海がある(昭和十一年)
(『神戸・続神戸・俳愚伝』より抜粋)
言葉に力があり、俳句に興味を持たない人でも、強く心を動かされるに違いない。
神戸での不思議な暮らし
俳人として活躍していた三鬼だったが、42才のとき、突如、それまでの生活を終焉することにする。生活の糧である歯科医も辞め、妻子を捨て、東京を出て神戸に向かい、軍需産業のブローカーとして働き始めるのだ。
その理由を彼はこう説明している。
昭和十七年の冬、私は単身、東京の何もかもから脱走した。そしてある日の夕方、神戸の坂道を下りていた。街の背後の山へ吹き上げてくる海風は寒かったが、私は私自身の東京の歴史から解放されたことで、胸ふくらむ思いであった。
(『神戸・続神戸・俳愚伝』より抜粋)
自由と言えば自由。でたらめと言えばでたらめな生き方に、自ら身を投じたことになる。
その後、三鬼は神戸のホテルで暮らすようになった。そこは、様々な事情を抱えた人びとが長期滞在している奇妙な場所だった。ホテルというより、多国籍な人物が集まる吹きだまりのようなところと言ったほうがいいかもしれない。三鬼も同じような立場だったから、たどり着くべくして着いたと言うべきか……。
国籍は、日本人が十二人、白系ロシヤ女一人、トルコタタール夫婦一組、エジプト男一人、台湾男一人、朝鮮女一人であった。
(『神戸・続神戸・俳愚伝』より抜粋)
職業も様々で、病院長、バーのマダム、肉屋など。いったいどうやって食べているのか、はっきりわからない人が好き放題に暮らしていた。中には、たとえ故郷へ帰りたくても許されず、身動きがとれないまま、ただ呆然と日々を送る外国人もいた。
思えば悲しい毎日だ。いったい明日、どうなるのか見当もつかない不安な日々を送らざるをえないのだから。ところが、三鬼の描くホテル生活は奇妙に明るい。食べる物に不自由している人もいれば、売春婦として生きる女性もいたが、彼らは彼らなりの倫理観を持って、堂々と生きている。そこに加わった三鬼は、周囲に「センセイ」と呼ばれ、頼りにされながら、毎日を過ごすようになった。
濃すぎるほどのキャラクター
『神戸・続神戸・俳愚伝』には、個性的というにはあまりにもすさまじい性格を持つ人達が、次から次へと登場する。「こんな人が本当にいたの? いていいの?」と、いぶかしく思うほどだが、本当に存在したのだろう。作り話や思いつきで構築できるキャラクターとは思えない。
私が一番興味をひかれたのは、ホテルの前に三日に一度、姿を表す人物だ。彼は一見したところは普通の男だが、ホテルの前にあるお気に入りの場所に来ると、いきなり服を脱ぎ捨て、ふんどし一枚になるや、天を仰ぎ、左の踵を軸にして、コマのようにグルグル回ってみせる。「なぜそんなことをするのか?」と問うても、「乱れた心が静まる」というわかったようなわからないような返事をするだけだ。めちゃくちゃな話だが、どこか救われるところがある。
実は、私も先日ひどく情けないことがあり、乱れた心を静めたくなった。そこで、着衣のままではあったが、彼の真似をして回ってみた、いや、回ってみようとした。しかし、果たせなかった。その回転は、想像していた以上に、高等技術を必要とする技で、運動神経の鈍い私にはできなかったのである。
ホテルに滞在しているエジプト人のマジット・エルバなる人物も面白い。彼はいつも極貧にあえいでいるのだが、突如、大金をふところに帰ってきては、皆に大盤振る舞いをする。しかし、翌日には早くもお金を使い果たし、一文無しに戻る。彼が稼いだときはいつも、どこかで牛が1頭、盗難にあっているという記事が新聞に掲載されるというのだから、どこで何をしているのやら……。
他にも、三鬼の恋人となった波子をはじめ、多くの奇矯な、しかし、魅力的な人物が登場するが、そのほとんどが悲劇的な運命に見舞われていく。あまりにも悲しくて、涙さえ出ない。涙より、吐き気に襲われるほどだ。それでいながら、残酷な運命を受け入れた人だけに許される、どこか突き抜けた明るさもある。
これから先、何度、本箱の掃除をしようとも『神戸・続神戸・俳愚伝』は生き残り、本箱の一等地に鎮座し続けるに違いない。大好きな一冊とは、私の場合、しぶとい本と同義のようだ。
【書籍紹介】
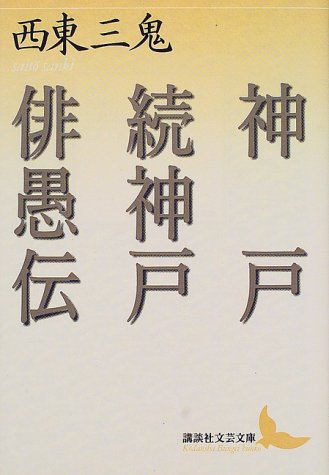
神戸・続神戸・俳愚伝
著者:西東三鬼
発行:講談社
“東京の何もかも”から脱出した“私”は、神戸のトーアロードにある朱色のハキダメホテルの住人となった。第二次世界大戦下の激動の時代に、神戸に実在した雑多な人種が集まる“国際ホテル”と、山手の異人館「三鬼館」での何とも不思議なペーソス溢れる人間模様を描く「神戸」「続神戸」。自ら身を投じた昭和俳句の動静を綴る「俳愚伝」。コスモポリタン三鬼のダンディズムと詩情漂う自伝的作品三篇。
