
人類史を振り返ってみれば、儀式と称して、残酷な処刑が数々行われてきました。
その中で最も悪名高い儀式の一つに、「血のワシ(blood eagle)」と呼ばれるものがあります。
これは中世ヨーロッパ時代にヴァイキングが行なった儀式と伝えられていますが、実は、本当にやっていたのかどうかは今もって分かっていません。
しかしこのほど、シカゴ大学(University of Chicago・米)の研究により、実際に「血のワシ」は実施可能であったことが示唆されました。
一体、どんな儀式なのか?
あまりにも血なまぐさいので、この先も読まれる方はご注意ください。
研究は、同大のプレスリリース『University of Chicago Press Journals』に掲載されています。
目次
- 「血のワシ」とは、どんな儀式なのか?
- 「実行可能だが、生贄はすぐに死んでしまう」
「血のワシ」とは、どんな儀式なのか?
「血のワシ」に関する考古学的な証拠や、あるいはヴァイキング自身の記録は一切見つかっていません。
それが記録されていたのは、スカルド詩とサガの中の記述のみです。
スカルド詩とは、9〜13世紀ごろの北欧(特にスカンディナヴィアとアイスランド)で読まれた古ノルド語による韻文詩のこと。
サガ(サーガとも)は、中世アイスランドで成立した古ノルド語による散文作品群の総称のことです。
その方法はきわめて残酷で、まず、犠牲者を生きたまま台座の上にうつ伏せに寝かせます。
次に、鋭い刃物で背中を開き、脊椎から肋骨を切り離します。
そして、左右の肺を引きずり出し、まるでワシの翼のように広げるのだという。
その配置および、肺が最後にひらひらと動く様子が翼の動きに似ていることから、「血のワシ」と呼ばれるようになりました。
こちらは、スウェーデンのゴットランド島にあるヴァイキング時代の石碑で、上から3段目に「血のワシ」が図像が記されています。

拡大すると、このような感じです。

ただし、この儀式が文学上の作り話なのか、それとも本当にヴァイキングに伝わる慣習なのかは不明です。
専門家らの間では、何十年も「血のワシ」が伝説として退けられてきました。
これを実際にあったことと証明するのは、考古学的な遺物か、ヴァイキング自身の記述が見つからないかぎり不可能です。
そこでシカゴ大の研究チームは、別のアプローチから、つまり「血のワシは実行可能だったのか」という問いから調査しました。
そして導き出された答えは「イエス」です。
「実行可能だが、生贄はすぐに死んでしまう」
チームは、現代の解剖学と生理学の知見をもとに、「血のワシ」の儀式が生きた人間に与える影響を調査。
その結果、儀式そのものは非常に難しいが、当時の道具や技術であっても十分に実行可能であると結論されています。
まず、チームは、背中をすばやく切り開く道具として、ヴァイキングの槍の穂先を使用したのではないかと考えました。
ヴァイキングが使用した槍は遺跡からいくつも出土しており、非常に鋭利だったことが分かっています。

その一方で、どれだけ背中をすばやく丁寧に切り開いたとしても、犠牲者はすぐに死んでしまうことが示されました。
原因は、心身のショックおよび出血多量です。
そのため、肺を取り出してワシの翼のように広げたりするプロセスは、すでに絶命した遺体になされたのでしょう。
肺がひらひらと動く、最後の”羽ばたき”も起きなかったと見られます。
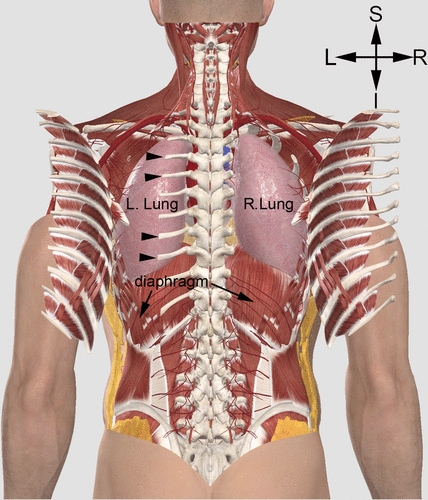
それでも十分に残酷でありますが、研究チームは「ヴァイキングの戦士なら何のためらいもなく実行できたろう」と述べています。
ヴァイキングの遺跡からは、これまでに、人為的に処置を加えた人や動物の遺体がたくさん見つかっています。
たとえば、ビルカ(Birka、スウェーデンにあるヴァイキング時代の都市遺跡)の地で発掘された10世紀頃の貴婦人の遺体。
彼女は身なりが綺麗に整えられていましたが、生前に斬首された頭が、右脇に挟まれた状態で安置されていました。
また、斬首の際に失われたと見られる顎骨が、ブタの下顎で代用されていたのです。
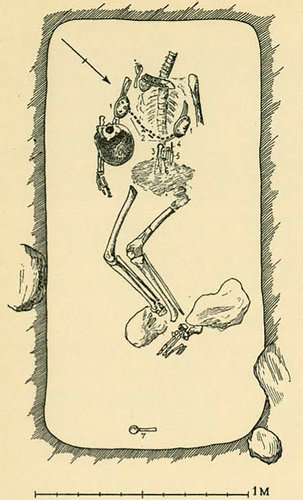

これだけ遺体を扱えるヴァイキングですから、「血のワシ」を実践していたとしても何ら不思議ではありません。
参考文献
Brutal Viking Ritual Called ‘Blood Eagle’ Was Anatomically Possible, Study Shows
https://www.sciencealert.com/brutal-viking-torture-method-anatomically-possible-concludes-new-research
元論文
An Anatomy of the Blood Eagle: The Practicalities of Viking Torture
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/717332
