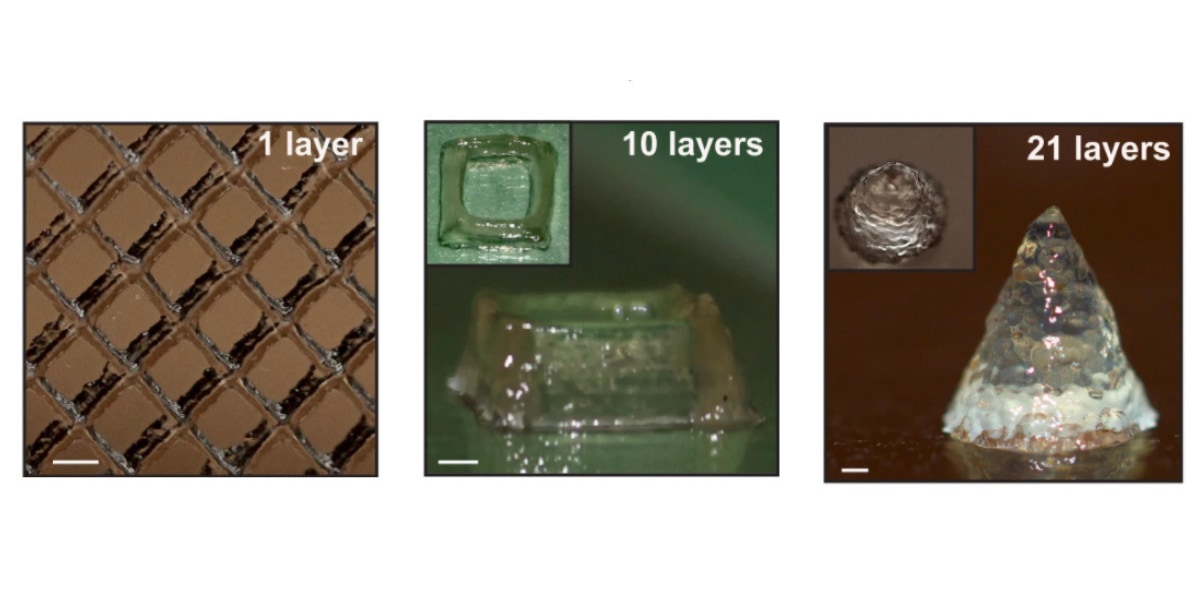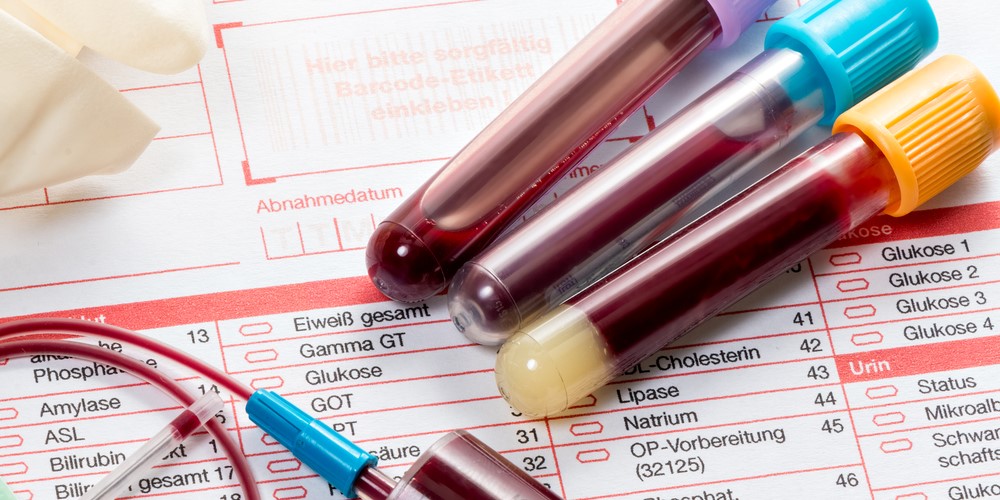バイアグラといえば、広く知られているED(勃起不全)治療薬です。
そのバイアグラが、EDとはまるで無関係の意外な症状に効果を発揮する可能性が明らかとなりました。
米国クリーブランドクリニック(Cleveland Clinic)の研究者が主導した新たな研究は、バイアグラの有効成分シルデナフィルを服用した場合、非使用者と比較してアルツハイマー病の発症リスクが約70%低下していると報告。
これは720万人を超える大規模研究から示されたもので、シルデナフィルがアルツハイマー病(AD)の予防と治療に役立つ有望な薬剤候補である可能性を示すものです。
研究の詳細は、12月6日付で、科学雑誌『Nature Aging』に掲載されています。
目次 バイアグラの意外な効能予防法が見つからないアルツハイマー病 バイアグラの意外な効能 アルツハイマー病とバイアグラというのは、一般的な認識ではま…
参考文献
Harnessing Endophenotypes for Alzheimer’s Disease Drug Repurposing
https://www.lerner.ccf.org/news/details/?Harnessing+Endophenotypes+for+Alzheimer%E2%80%99s+Disease+Drug+Repurposing&76a77dde946648f22990f170b9414613b9b8c440&48b73ec132819095396f4eb49f0c61ddc71c2b58
元論文
Endophenotype-based in silico network medicine discovery combined with insurance record data mining identifies sildenafil as a candidate drug for Alzheimer’s disease
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00138-z