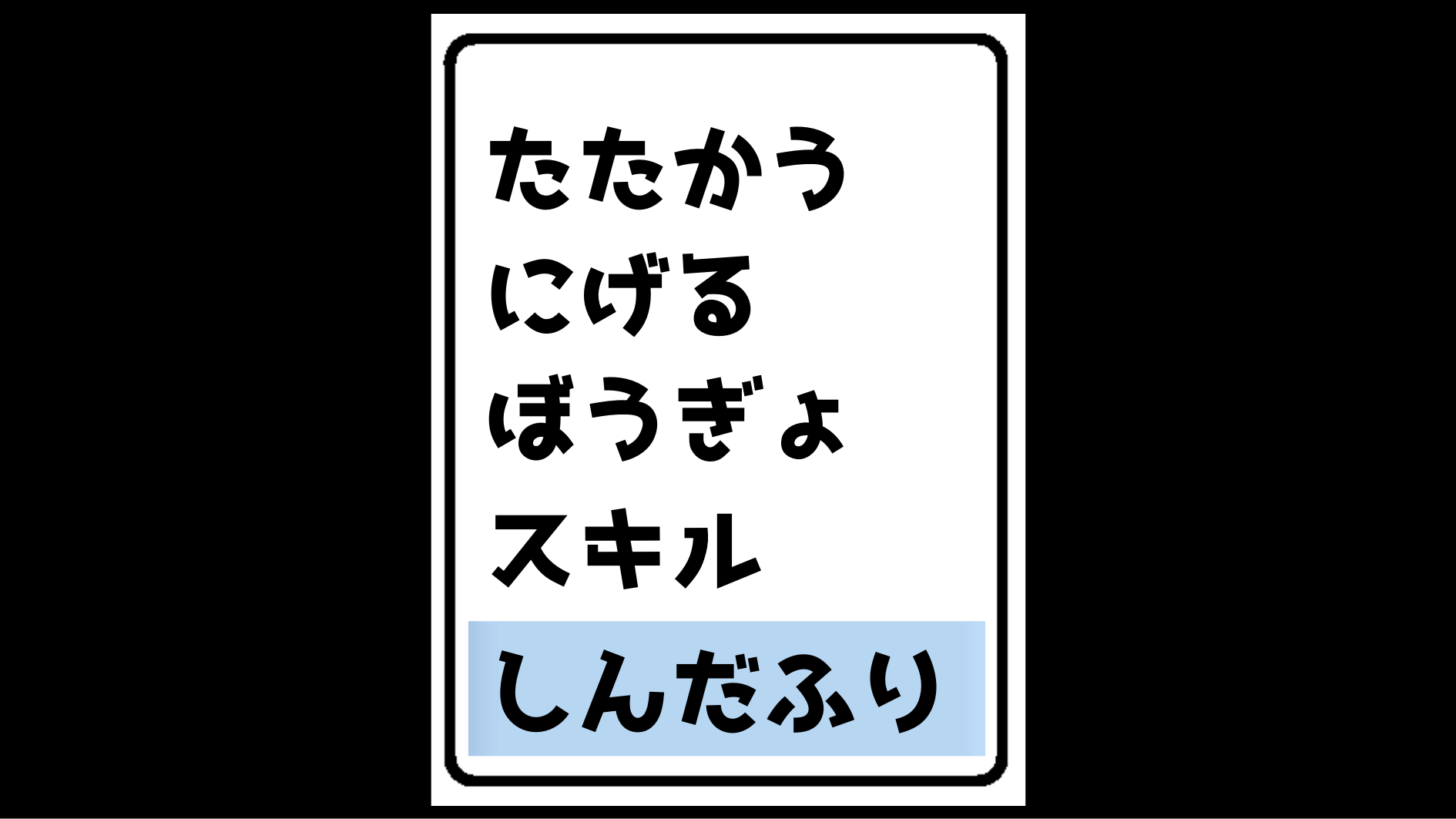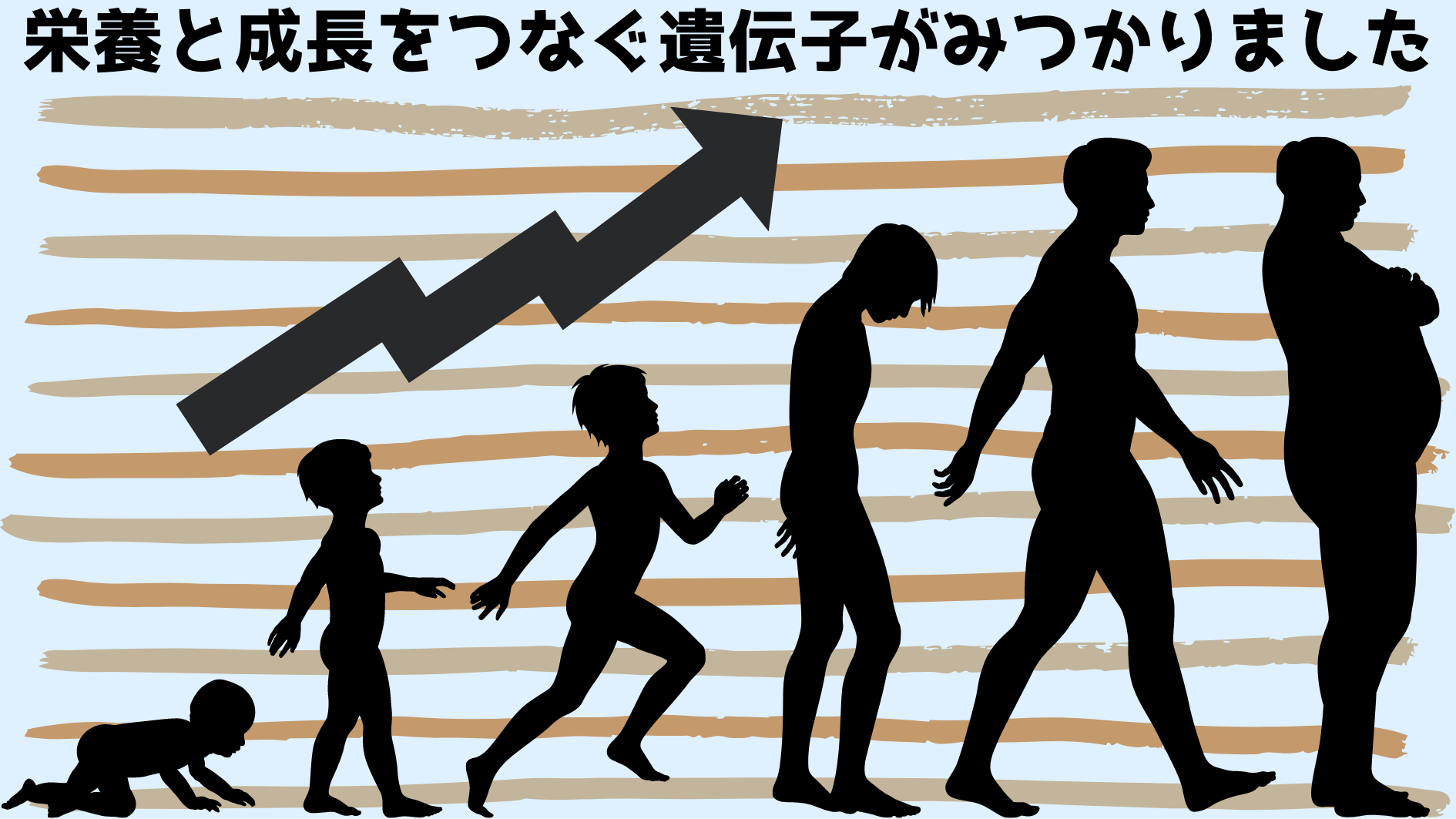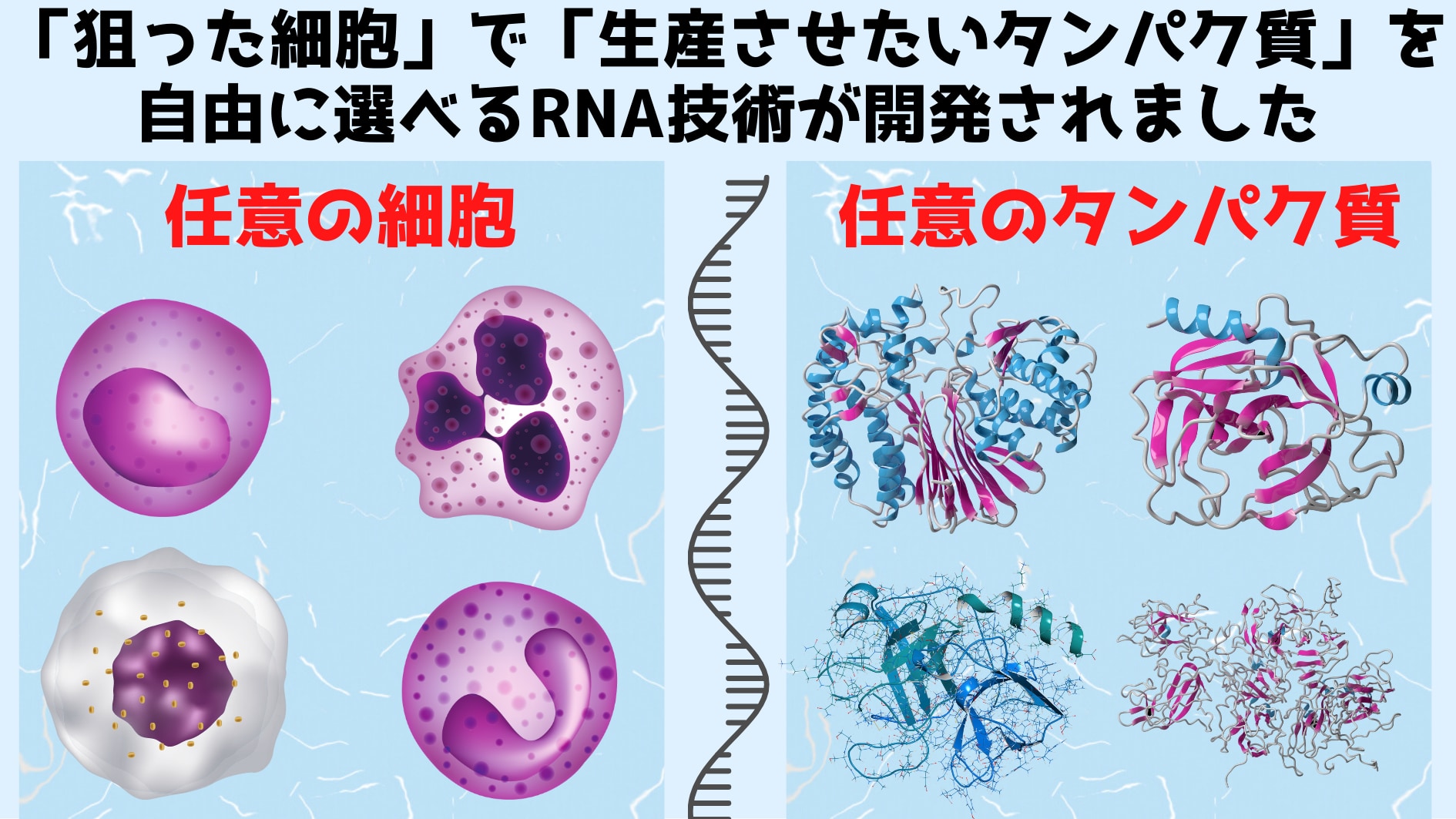光で記憶が消せるようになりました。
日本の京都大学で行われた研究によれば、脳の特定の場所に光をあてることで、マウスの特定の時期に形成された記憶を消去することに成功した、とのこと。
映画「メン・イン・ブラック」では閃光を放って記憶を消す装置「ニューラライザー」が登場しますが、現実の世界でも同じことができるようになるかもしれません。
研究内容の詳細は11月11日に『Science』に掲載されました。
目次 光でマウスの記憶を消すことに成功! SFの世界に一歩前進!マウスの脳に細い光ファイバーを刺し込む長期記憶は2日目の夜に作られる 光でマウスの記…
参考文献
Using optogenetics, scientists pinpoint the location and timing of memory formation in mice
https://www.statnews.com/2021/11/11/using-optogenetics-scientists-pinpoint-location-timing-of-memory-formation-in-mice/
元論文
Stepwise synaptic plasticity events drive the early phase of memory consolidation
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj9195